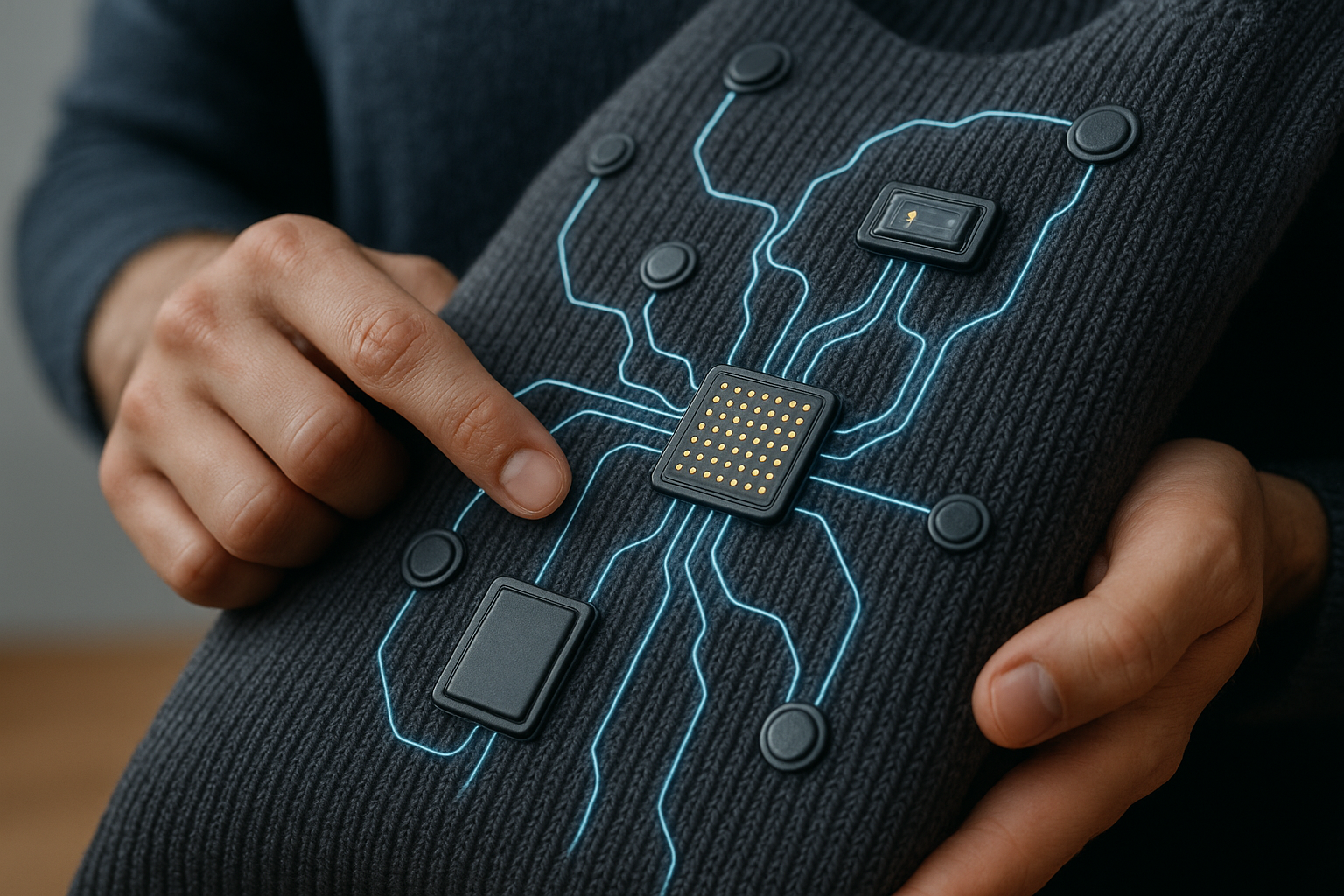2026年の日本における白内障手術の費用と方法
白内障手術は日本の高齢化社会の進展に伴い、年々その件数が増加しています。近年の技術革新により、手術方法もより安全で効果的なものへと進化し、使用される眼内レンズの種類も非常に多様化しています。本稿では、2026年時点における日本国内の白内障手術にかかる費用の相場や、保険適用の範囲について詳しく解説するとともに、最新の手術技術や眼内レンズの特徴についても客観的な視点から紹介していきます。

白内障手術とは
白内障は水晶体が濁ることで視力が低下する眼の疾患で、加齢によって発症率が高まります。手術は濁った水晶体を摘出し、人工の眼内レンズ(IOL)を挿入する方法が一般的です。日本では高齢化に伴い白内障手術の件数が増加傾向にあります。
手術費用の概要
手術費用は選択する眼内レンズの種類や手術方法、受診する医療機関により異なります。2026年の日本では、費用は数万円から数十万円台まで様々で、保険適用となる基本的な手術と保険適用外の追加選択肢によって幅があります。費用には術前検査、手術本体、レンズ代、術後の一定期間の検査などが含まれますが、施設によって内容は異なります。
保険適用範囲
日本の公的医療保険は、単焦点レンズを用いた標準的な白内障手術に対して適用されます。患者負担は通常3割で、片眼の自己負担は約4万から6万円程度が一般的です。一方、多焦点レンズや特殊なレーザー手術は自由診療になり、保険の適用対象外となるため、費用は自己負担となります。
眼内レンズの種類と特徴
単焦点レンズ
単焦点レンズは遠方または近方のいずれかの焦点に合わせる設計で、一般的な保険適用レンズです。術後は老眼鏡が必要となることがありますが、比較的副作用が少ないとされています。
多焦点レンズ
多焦点レンズは遠方・近方の両方に焦点を合わせられる設計で、メガネの依存度を下げることが期待されます。ただし、夜間の光のにじみ(ハローやグレア)が生じる場合があり、費用は自由診療となります。
その他のレンズ(調節型レンズ、乱視矯正レンズなど)
これらは特殊な機能を持ち、患者のライフスタイルに応じた選択肢として存在しますが、いずれも保険適用外となります。
手術方法の種類
従来法(超音波乳化吸引術)
白内障手術の基本的な方法で、濁った水晶体を超音波で砕いて吸引し、眼内レンズを挿入します。多くの医療機関で採用されています。
フェムトセカンドレーザーを用いた手術
レーザーを使って水晶体の切開や摘出部分の作成を補助する先進的な手術法です。手術の正確性向上が期待される一方、保険適用外であるケースも多いです。
その他の技術
状況に応じて微小切開技術や新しい器具を用いる場合があります。手術の安全性は医師の経験と施設の設備に大きく依存します。
医療機関および医師の選択基準
患者にとって重要なのは症例実績の多い医師や施設を選ぶことです。大都市圏には実績の多い施設が多い傾向がありますが、地方にも質の高い医療サービスを提供する医療機関があります。選択の際には医師の専門性、手術件数、術後ケア体制など客観的な情報を基に判断するとよいでしょう。
術前・術後の管理
手術前の詳細な検査で眼の状態を評価し、最適なレンズや手術方法が検討されます。術後は視力回復や合併症の有無を定期的に検査し、経過観察が行われます。一般的に術後数ヶ月間のフォローが重要とされています。
2026年の日本における白内障手術の典型的な費用
白内障手術の費用は選択内容により異なりますが、参考として以下のような分類がみられます:
- 基本的な単焦点レンズによる手術:自己負担で約4万〜6万円(保険適用3割負担の場合、片眼)
- 多焦点レンズなどの自由診療レンズを使用した手術:数十万円から50万円以上の費用がかかることが一般的
- 先進的なレーザー補助手術:施設や手術内容によって追加料金が必要となる場合がある
注意点
白内障手術の費用や内容は医療機関によって異なり、保険適用範囲も限定的です。手術の適応や方法の選択は医師の診断によります。また、レンズ選択によって術後の見え方や副作用のリスクが異なるため、十分な説明と理解が重要です。
まとめ
2026年の日本において、白内障手術は高齢化社会の進展とともに需要が増加しています。手術方法や眼内レンズは多様化しており、患者の状態や生活に応じた適切な選択が必要とされています。費用面では保険適用される標準的な手術と、自由診療となる追加的な選択肢があり、全体の内容の把握が求められます。術前検査や医師の専門性を踏まえて判断することが重要です。