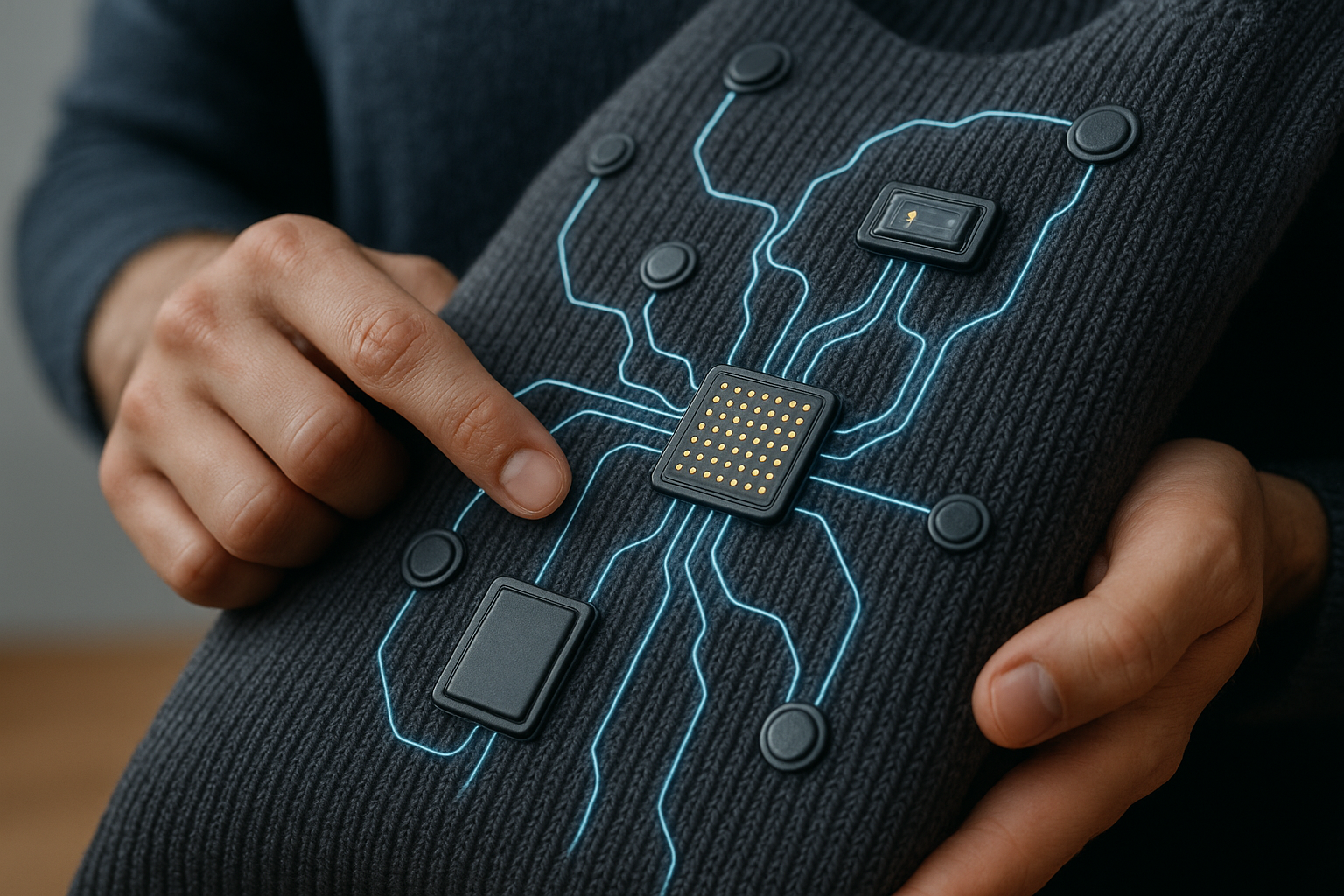2025年に学ぶ日本の放棄された家の取得方法と相続登記のポイント
日本では2024年4月1日から「相続登記」が義務化され、相続によって取得した不動産の名義変更手続きは3年以内に完了しなければならなくなりました。この法改正は、長年社会問題となっている所有者不明土地や空き家問題の解消を目的としています。したがって、放棄された家を取得するためには、まず相続登記の適正な手続きを理解し、相続人が誰であるかを確定し、名義変更を行うことが不可欠です。

本記事では、2025年における放棄された家の取得方法について、相続登記の義務化の背景から具体的な手続き、必要書類、費用、注意点まで詳しく解説します。
放棄された家を取得するために知っておくべき相続登記の義務化
- 2024年4月からスタートした相続登記義務化不動産を相続した場合、その名義を法務局で3年以内に変更(登録)することが義務化されました。義務違反には10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 義務化の目的多くの不動産が適切に登記されず、所有者不明となる「所有者不明土地」が全国で約410万ヘクタール(九州の面積超)にも及び、公共事業や民間開発、空き家管理等に支障をきたしています。これを解決するための法改正です。
- 放棄された家の取得と相続登記の関係放棄された家とは、長期間管理や登記がなされていない空き家のことを指します。こうした家を取得するには、法的に所有者が誰であるかを明確にし、名義を変更する必要があります。相続登記が済んでいない物件は、登記簿上の所有者が実際の権利者と異なる場合が多いため、まず相続人や権利者を確定し、相続登記を進めることが取得の第一歩です。
放棄された家を取得する際の具体的な手続きの流れ
1. 不動産の名義人と現状の把握
- 法務局で対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現所有者を確認します。
- 長期間登記されていなければ相続登記が未了の可能性があり、所有権の所在がはっきりしないことがあります。登記事項証明書は法務局のオンラインシステム「登記情報提供サービス」でも取得可能で、時間をかけずに利用できます。
2. 相続人の確定作業
- 放棄された家の前所有者(被相続人)の戸籍謄本や除籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、相続関係を整理します。
- 法定相続人が誰であるかを確認し、全員の同意形成の有無も含め検討します。2025年現在では、一部の自治体や法務局が相続関係の整理支援サービスを行っている場合もあり、これらを活用すると作業がスムーズになります。
3. 遺産分割協議
- 所有者不明や共有名義の不動産の場合、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書を作成し、全員の実印押印と印鑑証明書を集めます。
- 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判や、「相続人申告登記」制度を利用して一部手続きを進めることもできます。特に遠隔地に住む相続人との連絡が困難なケースも多いため、専門家による仲介が効率的です。
4. 相続登記申請
- 相続関係が確定した後、必要書類を揃えて法務局に相続登記の申請を行います。提出書類の不備があると、申請が長引くため、細部まで注意が必要です。
- 2025年現在では、オンライン申請も可能な場合が増えており、法務局や司法書士のサポートを受けながら活用すると便利です。
相続登記申請に必要な主な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票(住所確認用)
- 登記事項証明書(不動産の現状確認用)
- 遺産分割協議書(共有者がいる場合)
- 遺言書(ある場合)
- 登記申請書(法務局所定の書式)
- 印鑑証明書(相続人全員分)
書類取得時は、規定の有効期間があるため、申請まで期限切れにならないよう最新のものを用意しましょう。
相続登記にかかる費用の目安
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%程度(例:評価額3,000万円の場合、約12万円)
- 書類取得手数料:戸籍や住民票の発行に1~2万円程度
- 司法書士報酬:10万円前後が一般的(依頼内容や複雑さにより異なります)
なお、空き家取得に伴う固定資産税や都市計画税の負担も継続するため、費用全体の見積もりに含めておきましょう。自治体によっては空き家の活用支援や税の軽減制度もあり、活用の際は情報収集が重要です。
共有名義や複雑なケースでの注意点
- 共有名義不動産の場合、持分ごとに相続人が異なることも多く、登記内容が複雑になることがあります。
- 持分を単独所有に変更するには遺産分割協議や代償分割の手続きが必要です。
- 共有者間で連絡・協力が得られない場合、手続きが滞ることもあるため、専門家への相談を検討しましょう。
- 特に多数の相続人がいる場合は、連絡調整や書類の手配に時間と労力がかかるため、早めに計画を立てることをおすすめします。
相続登記の義務と延期・例外の対応策
- 3年以内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますので、期限内の手続きが望ましいです。
- 正当な理由がある場合は過料が科されないこともありますが、個別に法務局との相談が必要です。
- 相続人全員の同意が得られず遺産分割協議ができない場合、「相続人申告登記」制度を活用し一部の手続きを進めることが可能です。これにより、所有者不明土地問題のさらなる拡大を防ぎ、早期に登記情報を更新できます。
空き家・放棄された家の活用や売却に関するポイント
- 放棄された家を取得した後は、維持費や固定資産税の負担、管理責任が発生します。不要な場合は売却や利活用を検討するのも一つの方法です。
- 空き家の賃貸活用やレンタルスペース化、カフェやシェアハウスなどにリノベーションするケースも増えています。地域の住民との連携や自治体の支援を受けることで活用しやすくなるでしょう。
- 国や自治体の「空き家バンク制度」や補助金制度を利用すると、活用や売却がしやすくなることがあります。活用にあたっては最新の地方自治体の情報も参照しましょう。
- 2025年2月に開催される「すまいの終活フェスティバル2025」などでは、空き家の管理・処分・活用方法について専門家の解説があり、参考にできます。こうしたイベントやセミナーへの参加も知識習得に有効です。
専門家の活用と相談のすすめ
- 相続登記の手続きは書類の準備が多く、複雑なケースもあるため、司法書士などの専門家に相談や依頼をするのが効率的で安心です。
- 無料相談窓口やLINE、電話相談も利用可能で、まずは現状把握のために相談するのもおすすめです。
- 専門家は法改正情報に詳しく、書類の不備や申請遅延によるリスクの軽減に役立ちます。特に2025年の最新制度や地方自治体の対応について情報を持っているため、有益な提案が期待できます。
最新の制度動向と今後の相続登記義務化関連の動き(2025年以降)
2025年以降、相続登記制度はさらに利便性と正確性の向上を目指して、いくつかの新制度や改正が予定されています。例えば、
- 住所変更登記の義務化(2026年4月開始予定)不動産所有者は氏名や住所の変更について、変更から2年以内に登記申請を行う義務があります。これにより、登記簿の情報が常に最新状態に保たれ、不動産の所有者情報の透明性が高まります。違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性がありますが、これも「正当な理由」があれば免除されることがあります。
- 所有者不明土地の情報提供強化2026年からは法務局が所有不動産記録証明書を交付し、個人や企業が自己の所有不動産の一覧を容易に把握できる仕組みが導入される予定です。これにより、これまで複数の市町村にまたがる土地の把握が困難だった問題が解消され、相続登記に必要な情報収集がスムーズになります。
- 電子申請やメールアドレス届け出の推進2025年4月21日から不動産所有者は登記申請時にメールアドレスの提供が義務付けられており、住所変更登記や通知の連絡手段として活用されます。これにより、登記関連の連絡が迅速に行われ、手続きの遅延や通知漏れを防止できます。
こうした動きは、相続登記の義務化に伴う課題を解消し、空き家問題や所有者不明土地の問題に対してより効果的な対策を講じるために不可欠です。2025年の今、その準備や理解を進めておくことが、放棄された家の取得やその後の管理・活用を成功させる鍵となります。
最後に:放棄された家の取得には早めの対応が大切
2025年現在、相続登記の義務化により空き家や放棄された家の所有権問題はより明確に管理されるようになりました。放棄された家の取得を検討する際は、
- 名義の確認と相続人の確定を行い、書類取得から遺産分割協議まで丁寧に進め
- 期限内に相続登記を申請し、遅延を回避し
- 必要に応じて司法書士等の専門家のサポートを得て手続きをスムーズに行い
- 将来的な活用計画や税負担の管理も考慮した計画的な管理を行う
ことが重要です。法改正の趣旨をよく理解し、早めに適切な手続きを進めることで、複雑なトラブルを避け、円滑な取得につなげられます。放棄された家は、正しい手続きを踏めば新たな資産や地域活性化のきっかけになる可能性も秘めています。
Sources
免責事項:このウェブサイトに含まれるすべてのコンテンツ(テキスト、グラフィックス、画像、情報)は、一般的な情報提供を目的としています。このページに含まれる情報および資料、ならびにそこに記載された条項、条件、説明は、予告なしに変更されることがあります。